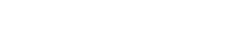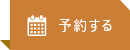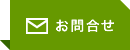よくある質問 faq

虫歯などで「神経」をとった後にどんな治療をするのですか
良く聞く「神経をとる」という表現。
神経とは何か。神経をとった後にどんな治療をしているのか、簡単にお話しましょう。
1)いわゆる神経ってなんでしょう
2)「神経をとる」のはこんなときです
3)神経=歯髄を取った後の治療
4)神経が入っていた穴=歯髄腔を閉鎖する処置
5)神経を取った後に噛めるようにする治療
1)いわゆる「神経」ってなんでしょう?
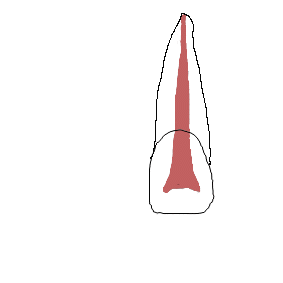 こんな絵を見た事は
こんな絵を見た事は
ありませんか?
中のピンクの部分が
いわゆる「神経」です。
・神経って?
よく、歯の治療で神経をとると言った表現を聞くと思います。
「神経ってなんだろう」 と思ったことはありますか?
歯の外側は硬い組織ですが、その中には歯髄と言われる軟組織が入っています。
この中には血管や神経などがあります。この組織は、歯の感覚や栄養を司っています。「神経」と呼んでいるのはこの軟組織の事です。
・大きな虫歯になると
「神経」にも細菌感染が起こり、強い痛みが起こることが有ります。また、そのまま放置すると、「神経」が壊死したり、歯の根の先に炎症を起こしたりすることもあります。
・神経をとるというのは
細菌感染が進んで行くと、壊死した「神経」はもとに戻らなくなります。この組織を除去して行う治療を「神経をとる」と表現しています。
2)「神経をとる」のはこんなときです
では、どのような症状の時、「神経」をとるのでしょう?
・神経が細菌に感染した時
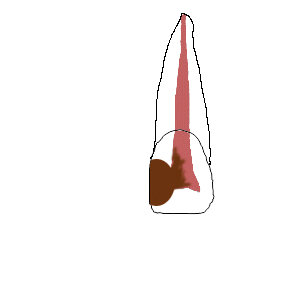 このような場合、
このような場合、
暖かい物や甘い物がしみたり、何もしていないのにずきずき痛んだりします。
「神経」が細菌に感染し、炎症の症状が表れていると考えられます。
虫歯の大きさは、歯髄腔と呼ばれる「神経」の入っている場所に及んでいます。
・歯の周囲の組織に炎症が及んでいる時
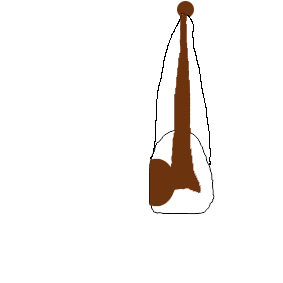 細菌に感染した状態で放置すると、「神経」は壊死してしまい、歯の根の先から周囲の骨に炎症が広がって行きます。
細菌に感染した状態で放置すると、「神経」は壊死してしまい、歯の根の先から周囲の骨に炎症が広がって行きます。
炎症は次第に広がり、骨の吸収を起こして行きますが、ふだんは重苦しい感じがしたり咬むと嫌な感じがする程度です。
ある日、急に痛みや歯茎の腫れ、歯の動揺、頬の腫れといった急性症状を呈することもあります。
レントゲンをとると、根の先に病巣が出来ていることがわかります。
・神経が壊死した時
虫歯ではなく打撲などが原因で「神経」の壊死が起こることがあります。細菌感染がない場合、強い症状が表れることは稀ですが、次第に歯の色が黒ずんできます。
放置すると歯の周囲に炎症が広がることがあるので、このような場合にも「神経」をとることがあります
3)神経=歯髄を取った後の治療
続けて 神経を取った後の治療について説明します
歯科医院で「神経を取りましょう」と言われると、ちょっと悲しい気持ちがしませんか。
神経を取った歯は、健康な歯と全く同じ状態とは言えません。
けれども、神経を取った後も、できるだけ長く今までと同じように噛めるように、最後まできちんと治療を受けて下さい。最後まで治療を終了させずに放置すると、歯の周りの組織に細菌感染、炎症が広がって行く可能性があります。
・機械的にきれいにする
歯の中には「歯髄腔」と呼ばれる空間があります。この中には健康な状態では歯髄(=いわゆる神経)と呼ばれる軟組織があります。細菌に感染したり壊死をしたりした歯髄はまず、機械的に取り除かれます。
様々な器具を用いて、歯髄腔の中の歯髄を除去し、空洞にします。この時、軟組織を根の先から押し出さないように慎重に行う必要があります。また、最終的に歯髄腔を閉鎖する必要がありますので、その際の治療が行い易い形態に整えておきます。
・消毒する
細菌を取り除くためには、機械的にきれいにするだけでは足りないと思われます。消毒作用のある薬品を用いて洗浄をしたり、歯髄腔に数日間塗布して経過を見たりします。消毒が十分に行われ、症状がなくなった時点で、歯髄腔を閉鎖する処置に移ります。
最近はレーザーや高周波治療器を用いて、熱、電気の作用で消毒する事もあります。
4)神経の穴=歯髄腔を閉鎖する処置
歯の根の中がきれいになったら、空洞を閉鎖する治療に移ります。
根の先まで緊密に閉鎖し、細菌は入ることが無いようにします。
・閉鎖する材料
材料にはいろいろな種類がありますが、根の先から外に漏れないように、また、空洞のなかに隙間が残らないように丁寧に充填されます。
生体に為害性のない材料で、このような操作に適した材質のものが用いられます。ガッターパッチャと言う天然素材を基にした材料がよく使われます。
・レントゲンの撮影
通常、このような処置が終わった後にはレントゲンの撮影を行い、緊密な閉鎖が行われたかどうかを確認します。もし、不足が有った場合には再度充填を行うことになります。
・治療の後の痛み
歯髄腔の閉鎖を行った後、1、2日浮いたような感じや、咬んだ時の不快感があることが有りますが、通常しばらくでおさまります。これは、根の先まで薬をつめたために圧力が加わっているためと思われます。もし、痛みが無くならないようで有れば、再度根の治療をやり直さなければならないかもしれません。
・神経の治療の後
このままでは、今までのようにものを咬むことはできませんから、もう一度、今までのような形に治さなければなりません。
5)神経を取った後に噛めるようにする治療
神経の治療を終えてもそのままでは咬むことができません。もう一度、虫歯になる前の形にしなければなりません
・冠をかぶせる治療
普通、神経の治療が必要な歯は虫歯などで元々の歯の形が損なわれています。そこで本来の歯の形に戻すために、冠を被せます。
ところが、神経の処置をした歯は、次第に乾燥し脆くなっていきます。この様な歯に力がかかっても大丈夫なように中心に心棒になる金属の土台をいれます。その上に歯の形をした冠を被せます。
保険診療では糸切り歯までの前歯は合成樹脂を用いて白い外見に、それより奥の歯は金属の歯に治すことになっています。
保険外診療では材料の制限はありませんから、奥の歯でも白い陶材の歯にすることができます。
但し、その人の歯並びの状態によっては、奥歯を白い歯にするだけの厚みがとれないこともあります。冠を被せる治療に移る前に、担当の歯科医師と良く相談して、どのような冠を被せるのかをきめて下さい。
・冠をかぶせない治療
虫歯以外の原因で神経が壊死し、歯の外側がほとんど損なわれずに残っている場合や、まだ歯並びの出来上がっていない非常に若い時期に神経の処置を行った場合には、冠を被せない場合もあります。
歯が残っている場合には、神経の治療に必要な最小限の量の歯を削って治療を行い、その部分に何かを詰めて終わることになります。また、噛み合わせが出来上がっていない時は、歯が生え揃うまでの期間、暫定的に何かを詰めて、歯並びの完成を待つことになります。
詰めるものには、色々な材料がありますが、合成樹脂、アマルガム、金属などを用います。
どちらの場合も、歯が欠けてきた様な時には、冠を被せる治療に移っていきます。また、暫定的に詰めたものは、最終的には冠を被せる予定ですから、定期的に噛み合わせの状態のチェックを受けて、適切な時期に冠を被せてください。
神経の治療が終わった歯は、神経の生きている歯とは色々違うところが有ります。何か気になる症状がある場合には、早めに歯科医師に相談して下さい。