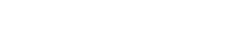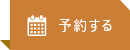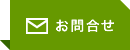よくある質問 faq

小さなお子さんが初めて歯科医院を受診する時は
初めて歯科を受診するお子さんは知らない場所にやってきて少し緊張しています。付き添っていらっしゃる保護者の方も少し不安でしょう。
そして、歯科医院のスタッフも、少し緊張した気持ちでお待ちしています。
初めての歯科受診の前に知っておくと役に立ちそうなことを少しピックアップしてみました
1)初めての歯科
2)予約の取り方
3)受診の前に
4)小児歯科治療
5)衛生指導
6)予防処置
7)定期検診
1)初めての歯科
どんな時に初めて歯科にいくのでしょう
・歯科医院へ行く年令
何歳くらいから見てもらえますかと聞かれる事があります。
初めて歯科医院へ行く年令は、早い方で1歳前後です。もちろん全く歯科医院に縁のない状態で大人になる方もいらっしゃいますが、最近は虫歯のないお子さんのほとんどが、早くからなんらかの形で予防処置を受けているのではないでしょうか。
虫歯がないかどうかの検査、歯ブラシなどの指導、簡単な予防処置は、対象が幼いお子さんであっても十分可能です。
しかし、虫歯になった場合の治療を、嫌がらずに受けられるのは概ね三歳ぐらいから、恐怖心の強いお子さんの場合は4歳すぎになってようやくと言うことも少なく有りません。
・受診の理由
虫歯のために受診する方が、やはり一番多いのです。
虫歯に気がつくのは家庭の中でということもありますし、なんらかの検診~1歳半検診や、三歳児検診、幼稚園の歯科検診~で指摘されてと言う方もいらっしゃいます。
また、初めて歯科医院に見える時点で、既に痛みが出たり歯茎がはれたりといった大きな虫歯になっているお子さんもいます。
虫歯になる前に、と歯科検診や予防処置を希望して見える方もいらっしゃいます。早い時期から歯科医院で予防のためのプログラムに参加することで、お子さんに健康な歯を与えたいとお考えの家庭です。
数は少ないのですが、歯の外傷のために見える方も有ります。歯の外傷が起こりやすいのは、歩きはじめの1歳すぎから2歳くらいと、小学校に入るくらいの頃です。
そして、歯の形や数の異常ではないかなどの心配をしていらっしゃる方もあります。
・小児歯科の目標
患者さんの受診理由は様々ですが、小児歯科の目標はいつも、健全な永久歯列:健康な大人の歯並びです。
治療の方針は、その目標に沿って立てられます。治療の方針、治療の方法の説明をよく聞いてから治療を受けて下さい
2)予約の取り方
・歯科医院の選択
もちろん、電話の前にどこの歯科医院にかかるかを決めなければなりません。
兄弟がすでにかかっている子どもの治療をしてもらえる歯科医院があればそちらにかかられることになるでしょう。
お友達などにかかっている医院を聞いてきめるのも一つの方法です。
初めてのお子さんで見当がつかない時、お家の方の掛かり付けの歯科医院に御相談なさってもよろしいでしょう。その医院で見てもらえることもありますし、小さなお子さんは小児歯科の専門医に紹介して下さることもあります。
もし、見当がつかなければ、 NTTの電話帳で小児歯科の標榜医院を探す方法もあります。インターネットを利用する方法もあります。
【インターネットの利用】
◆全ての小児歯科がホームページを持っているわけでは有りませんが、歯科関係のリンク集、検索エンジンなどを辿っていくとたくさんの歯科医院のホームページが見つかります。お住まいの近くの歯科医院のホームページが見つかったら、目を通しておくとよいかもしれません。
http://itp.ne.jp/servlet/jp.ne.itp.sear.SCMSVTop
NTTのタウンページも最近はインターネット版があります
http://www.mmjp.or.jp/dental-surf/ds/index.html
歯科医院、歯科大学研究機関、関連企業、関連団体のリンク集
http://www.jpinfo.co.jp/me/index.ssi
メディカル電話帳
インターネット最大16万件
都道府県別、医療機関の電話帳
名称、住所、などから検索可能
http://home.hiroshima-u.ac.jp/pedo/jspd/default.htm
小児歯科学会のホームページ
学会認定医・専門医の名簿の掲載あり
・電話の前にメモを
歯科にかかる人の、名前、年令、性別など 個人情報
どんなことで困っているのか、何が心配なのか
痛みが有る場合は、いつから、どんな時に痛いのか
腫れが有る時は、いつから腫れているのか、排膿の有無
予防処置の希望が有る時は、何を希望しているのか
などを簡単にメモしておきましょう。
電話で聞かれなくても、問診の際などに役立ちます。
・予約の取り方
家の人の都合の良い時間を告げて、歯科の受付の人に予約をとってもらいます。希望の日時が埋まっていることも有りますので、予めいくつか候補を考えておくといいでしょう。
緊急を要する場合はその旨を告げましょう。電話した医院ですぐに時間がとれない場合、対応できる機関を教えてもらえるかもしれません。
忘れがちな事ですが、家の人の都合ばかりではなく歯科にかかる子供の体調なども考えて予約をとります。食事の直後や、いつも昼寝をする時間などは避けた方がいいと思います。
この時間が機嫌がいいと言う時間を選んでおきましょう。
3)受診の前に
初めて歯科医院へ出かける前は、ちょっと緊張することでしょう。
受診の前、歯科医院にでかける前に注意してほしいことがいくつかあります。
これは、全く歯科医院のサイドからのお願いですが・・・。
とにかく歯科医院を怖がらせるような言動をとらないでいただきたい。これに限ります。
初めて歯科医院にやってくる子ども達の中には、最初からとても緊張している子がいます。
本当に小さな1~2才のお子さんは、知らない場所に来ただけでナーバスになっていますが、年令の高いお子さんにも、そのような様子が見られることがあります。
どうも、おうちの方や、お兄さん、お姉さん、お友達などから、
「歯医者さんは恐い場所」という情報を得ている様です。
歯科医院では、できるだけ小さなお子さんに怖がられないように配慮をしています。できるだけ、恐い場所と言う印象を与えないように、お家の方にも御配慮をいただきたいと思います。
4)小児歯科治療
さあ、治療のはじまりです。
小児歯科の治療ではどんなことをするのでしょう?小さいお子さんでも、治療の基本は大人と同じです。
・治療の方法
治療の方法は大人と同じです。
基本的に、虫歯になっているところを取り去り、何か他のものに置き換えます。
神経が死んだり感染したりしている歯は、中をきれいに洗浄消毒して、薬を詰めます。残しておくことが難しい歯は抜歯の対象になります。
違うのは、乳歯の治療は永久歯の事を考えながら行うことです。
永久歯に悪い影響を与えないように、永久歯の成長の状態を確認しながら治療の方針を決定します。
・恐怖心への対応
大人の方と一番違うのは、恐怖心への対応に十分配慮することです。
(大人の方でも、歯科が恐いために治療が受けられない方は、事前に歯科医師にその旨をつげて対応してもらいましょう)
小さなお子さんの場合程、恐い思いをしないように、説明の方法を工夫し、少しずつ治療の器具などに慣れる様トレーニングをしてから治療に入ります。しかし、どんな小さなお子さんでも、緊急を要する症状が出ているような場合は、歯科への恐怖心を取り除くまで待っていられないこともあり得ます。その場合は、どのようにして治療を行うか、担当医と保護者の間でよく話し合い、了解の上で行うべきでしょう。
できるだけ、初めての治療で、歯科に対する恐怖心を植え付けないように、どの小児歯科医も最善を尽くしています。
5)衛生指導
虫歯を治したらさようなら?治療が終わったら、まず、衛生指導を受けましょう。
治療が終わったらもう歯医者さんには行きたくないと、どなたも思われることでしょう。
けれども、できればもう一回予約をとって、もし時間が無ければ最後の治療の日に、これから虫歯にならないようにするための指導を歯科衛生士に受けて下さい。
・何故、衛生指導が必要なのでしょう?
今までと同じ歯ブラシの仕方、同じ食生活を続けていれば、また同じような虫歯ができてしまいます。
何が原因になって虫歯ができたのか、生活習慣をよく見直しをしましょう。歯ブラシの仕方は、歯科衛生士がお子さんの歯の状態に合った方法を教えてくれるはずです。
一般的に虫歯になりやすいところ、そしてそのお子さんによって次に虫歯ができそうなところがあります。それぞれのお子さんに合わせて、何に気をつければ良いのか、どのような清掃を行えば良いのか、よく教えてもらいましょう。
清掃の方法も歯ブラシだけではありません。担当医には聞きづらかったような事がありましたら、この時に歯科衛生士に相談されてもよろしいかと思います。日常生活で注意することなど、きめ細やかな対応が期待できると思います。
・衛生指導の実際
衛生指導は、年令の低いお子さんでは保護者の方への指導が主体になりますし、6歳くらいからは本人への指導と家庭でのチェックの仕方がポイントです。いつまでも大人が歯ブラシをしてやるわけにも行きません。少しずつ自分で管理できるような体制に移行して行きましょう。
そのうち、大人のチェックを嫌がる時がやってきます。その時にどのくらい自分で管理できるようになっているかで、思春期の歯周病や虫歯の状態が決まってきます。
・衛生指導を受けてみませんか?
虫歯の治療が終わった時、どんなに治療に協力的だったお子さんでも、また治療を受けたいとは思っていないはずです。おうちの方も、また歯科医院に通院したりしたくはないはずです。
治療が終わった時点が、もう一度虫歯になるかどうかの分かれ目です。
さあ、お子さんにとって良いことはどんなことか、よく考えて下さい。
6)予防処置
予防処置は受けましたか?予防処置ってなんでしょう?
歯科で行われる予防処置は、予防注射のような免疫を作るものではありません
・フッ化物の局所応用
よく耳にするフッ素塗布や、フッ素洗口がこれに当たります。
歯のエナメル質に作用して、溶けにくい性質の物質に置き換える作用があると言われています。
フッ素塗布を行ったから、決して虫歯にならないという保証はありません。虫歯になりにくくする効果は期待できますが、甘いものをたくさん食べていたり、歯ブラシを全くしなかったりすれば虫歯をさけることは難しいでしょう。
中には、フッ素の毒性を指摘する方もいますが、私どもは、歯科で局所応用するフッ素の濃度と量では問題は無いと考え、患者さんにもすすめています。現在は、多くの歯科医院で予防処置として勧められると思います。
最終的には、フッ素を使うかどうかは、御自身で判断することになります。不安を感じる方はインターネットにもたくさんの情報がありますので、お探しになってもよろしいかと思います。その結果、御自分のお子さんにはなさりたくない、とお思いになった場合は、主治医に率直にその旨をお伝えになってください。
虫歯予防の方法は一つだけではありません。フッ素を塗らなくても、家庭での食生活や歯ブラシの習慣によって虫歯を避けることは可能だと思います。
・シーラント
奥歯の噛み合わせの凸凹になった部分の溝の、一番深い部分まで歯ブラシを届かせることは、実は、不可能です。歯ブラシの毛先の方が、ずっと太くしか作られないからです。
ところが、生えてまもない奥歯は、この部分に虫歯を作ってしまうことが非常に多いのです。
そこで考えられたのか、シーラントという方法です。合成樹脂などの材料で、歯の溝を予め埋めてしまいます。そうして、歯ブラシの届かない場所をなくしてしまうわけです。もちろん、シーラントをしても、歯ブラシをしなければ、同じことです。
7)定期検診
虫歯の治療も終わり、予防処置も済ませて、歯ブラシの指導も受けました。でも、本当は定期検診も受けていただきたいのです。
・定期検診の意義:定期検診はなぜ行うのか?
子どもの虫歯は、乳歯の構造のためもあって、永久歯にくらべて進行が早い傾向にあります。また、大きくなるにつれて、歯の状態はどんどん変化をしていきます。その時の歯並びの状態によって、虫歯になりやすい場所も変わって行きます。
虫歯になった時、神経の処置が必要になる前に治療ができるようにするためには、早い時期に虫歯を見つける必要があります。検診の第一の目的は、虫歯の早期発見です。なんといっても、子どもの場合は歯科で治療を受ける原因のほとんどが虫歯です。
次に、予防を目的として行います。今、虫歯があるのか、ないのか、虫歯がなくても、今にもできそうな状態になっていないかを、チェックします。必要に応じて予防処置を行い、また、虫歯にならないための指導を受けます。
さらに、永久歯への生え変わりの時期には、歯並びに何か心配な点がないかを確認します。歯の数や、生えてくる位置などを確認し、矯正の必要が無いかどうかも見て行きます。
・健康保険の適応
虫歯の多いお子さんの定期検診は健康保険で行うことができます。
(H20.4.1現在)
すべてのお子さんが対象ではありませんが、現在、定期検診やフッ素塗布もも保険診療の対象となる場合があります。
本来、予防を目的とする診療行為は健康保険の対象外となっています。しかし、虫歯の多いお子さんの再発を防ぐ目的で、継続的な指導が保険にも導入されてました。ただ、すべてのお子さんを対象とするには、財源に限りがあるのでしょう。
今のところ、年令の割に虫歯が多いと思われるお子さんで、虫歯の治療が終了している方を対象に行われています。ですから、兄弟で同じ虫歯の本数なのに、上のお子さんは保険が使えず、下のお子さんは保険診療になるという事も起こり得ます。制度が煩雑で判りにくいかと思いますがルールとしてご理解頂きたいと思います。
また、小学生までのお子さんの定期検診についての特例もありますが、保険制度は複雑ですのでかかりつけの歯科医院でご相談下さい。
・定期検診の間隔
そのお子さんの虫歯の本数、現在の清掃状態、年令などを考えて、定期検診の間隔が決められます。
虫歯が多かった場合や、虫歯が少なくても歯ブラシが上手に出来ていない時は、少し短かめの間隔で、あまり虫歯などの心配が無い時は長めの間隔での検診を勧められると思います。少なくとも、半年に一回くらいは検診を受けることをお勧めします。
大人の方と違い、お子さんの場合は半年前とは口の中の状態ががらっと変わってしまうこともあるからです。
もちろん、検診の時期の前でも、心配なことが有る場合は、早めに主治医に相談して下さい。
それでは、お子さんが健康な大人の歯並びに育たれることをお祈りします。